
フジ住宅の裁判・ブルーリボン訴訟とは?その経緯や判決結果について調査
このページでは、フジ住宅の裁判・訴訟の経緯や判決結果、ブルーリボン訴訟についてまとめています。
フジ住宅とは?事業内容や強みをチェック

フジ住宅株式会社の会社概要・事業内容はつぎの通りです。
| 商号 | フジ住宅株式会社 |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 社長執行役員 宮脇宣綱 |
| 創業/設立 | 昭和48年1月22日/昭和49年4月19日 |
| 本社所在地 | 〒596-8588 大阪府岸和田市土生町1丁目4番23号 事業者一覧 |
| 事業内容 | ■分譲住宅事業 ■住宅流通事業 ■土地有効活用事業 ■賃貸及び管理事業 ■注文住宅事業 |
| 資本金 | 48億7,206万円 |
| 上場取引所 | 東証プライム市場 |
| 従業員数 | 910名(連結1,247名)*パート社員含む |
| 公式サイト | https://www.fuji-jutaku.co.jp/ |
フジ住宅株式会社は、大阪府や兵庫県、和歌山県などの関西エリアを中心に新築一戸建てや分譲マンションの設計から建築、販売や不動産管理事業を展開する企業です。
戸建住宅事業においては、設計、建築だけでなく、土地の仕入から許認可、引き渡し後のアフターサービスのすべてを自社で行う一貫体制を構築しています。
同社の創業は1974年。創業から50年以上地域に密着し、事業を展開してきたフジ住宅が理念としているのが「売りっ放し、建てっ放しにない」ということ。
事業エリアを限定し、地域に密着してきたからこそできる、顧客ニーズにマッチした商品の開発やサービスが強みといえるでしょう。
そんな同社は、2003年に上場。東証プライム企業であるフジ住宅の2023年の売上高は、1,144億円(連結・3月期)、従業員数は1,247名(連結)。
「大阪府 住宅着工棟数 地域ビルダーランキング」17年連続No.1(2005~2021年度/(株)住宅産業研究所2007~2023年2月発表)の実績を誇る、大手不動産会社です。
フジ住宅裁判・訴訟とは?女性パート従業員が賠償金を求めて訴訟

長年、地域に密着し、豊富な実績を誇る総合住宅メーカーであるフジ住宅。
同社は2015年にパート従業員として働いていた在日韓人女性から訴訟を起こされています。
提訴した女性従業員は、フジ住宅が全社員に向けて配布していた社内資料のなかに民族差別にあたる内容があったとし、精神的苦痛を受けたとして3,300万円を請求。
2020年7月に第一審、2021年11月に第二審が大阪高裁で行われました。
判決は原告への132万円の支払い
フジ住宅は、2013年頃より社員教育、人材育成の一環として、インターネットや書籍、雑誌などのコピーを配布していました。
フジ住宅が裁判・訴訟を提起された原因となった資料とは
今回の訴訟の要因となったという配布資料は以下となります。
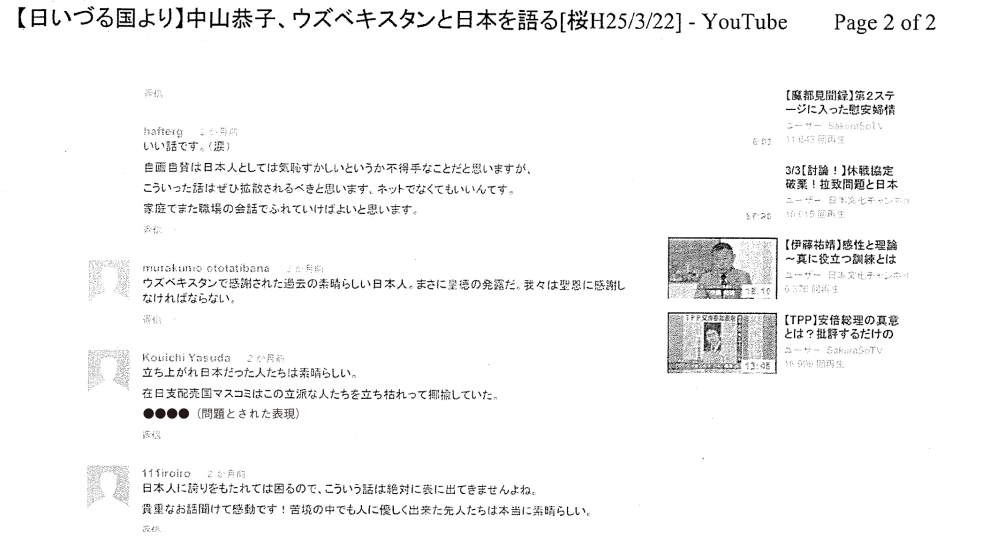
参照元:https://www.fuji-jutaku.co.jp/sites/default/files/2022-11/QandA_doc.pdf
訴訟の要因となったのは、「●●●●」(問題とされた表現)」という部分です。
フジ住宅側は公式サイトにて、以下のように主張しています。
社内で過去に配布した資料の中にそのような文言が入っていたのは事実ですが、一度だけであり、かつYouTubeを見た第三者の書き込んだコメントが偶然入り込んでいたものです。配布書面をお読みいただければ明らかだと思いますが、目的は動画の紹介です。(引用元)
これらの資料が原告に対する民族差別だったどうかが論点となった公判。
判決は、フジ住宅側の敗訴となり、原告への132万円の支払いが命じられました。
敗訴となったことから、同社がヘイトハラスメントをしたということが認められたと認識してしまうかもしれません。
しかしながら、大阪地裁は「程度や態様が社会的に許容できる限度ではないが、文書配布は女性個人に対する差別的言動とはいえない」としており、「マスコミの報道は不適切」としています。
原告の3,300万円の支払い要求に対し、132万円の支払い命令と、大幅な減額となっていることからも資料の配布は原告女性を誹謗中傷することを目的とするものではなかったと推測できます。
訴訟までの時系列はこちら
https://www.fuji-jutaku.co.jp/sites/default/files/2022-11/QandA_doc.pdf
ヘイトスピーチを含んだ文書に関して
先に紹介した文書以外にも、多数の文書について「ヘイトスピーチであることが明らかな資料」ないし「人種的民族的差別を助長する資料」であると原告は主張しています。
例として挙げられたのが「従軍慰安婦の強制連行」に関するものでした。
フジ住宅側は、ヘイトスピーチに関して否定しています。
上記サイト内の「職場での文書配布行為について」にて主張されていますが、非常に長いので要点をまとめました。
-
-
- 指摘された内容は、韓国に関する史実、意見論評など公益目的のものであり、差別表現の意図は全く含まれていない
- 原告はそういった「前提」抜きでそのまま言葉のみで受け止めている。
そこからヘイトスピーチ、差別表現であると主張されるのは不当な「言葉狩り」である - 日本に関する資料が多いのは「自虐史観の克服」のためである。
- 本件は「社員の成長」「会社の業績向上」に繋がっており、「業務と関連性がない」ことについては否定している
- 立場や考え方によっては「業務と関連性がない」と思うこともあるとは思うが、簡単に違法評価されるべきではない
-
また、フジ住宅は原告に対し、
「自身の主義主張に相容れない表現に接して主観的に不快であった」
「歴史認識や思想性の違いからくる不快感や感情的反発に過ぎない」と述べています。
「差別的」と取れるような単語・文章が実際に記載されていたとしても、表面だけで捉えるのではなく、どういった背景・前提でそのような表現が用いられたのかが重要ということだと思われます。
裁判においても、重要視されていた部分であると予想されます。
-
法廷でのブルーリボンバッジの着用をめぐった「ブルーリボン訴訟」とは

社内資料の配布をめぐった訴訟のほかに、もう1つフジ住宅にまつわる訴訟があります。
「ブルーリボン訴訟」と呼ばれるこの裁判は、フジ住宅が国に対して390万円の損害賠償を求め提訴したものです。経緯としては、パート女性が起こした裁判の法廷で、原告の支援者たちが「「ストップ!ヘイトハラスメント」とデザインされたバッジを付けていました。
それを見たフジ住宅側は、裁判官に注意してもらうように求めたものの、対応はありませんでした。
後日、フジ住宅側も富士山と太陽がデザインされたバッジを付けて入廷しました。
それを見た裁判官は双方のバッジ着用を注意し、ブルーリボンバッジの着用も禁止となりました。
ブルーリボンバッジとは、「北朝鮮の拉致問題解決を願う国民運動のシンボル」であり、今回の裁判とは全く関係のないものです。
裁判長には、法廷の秩序を守るための「法廷警察権」があり、お互いバッジを付けることで対立の激しさが増したことから、着用を禁止としました。
しかしながら「ブルーリボンは今回の裁判の争点と全く関係がない」として、フジ住宅は法廷警察権の乱用にあたると主張したのです。
世間の注目をあつめた「ブルーリボン訴訟」は、2023年5月の第一審では、請求を棄却され、2024年1月24日の大阪高裁での控訴審判決においても「法廷警察権の行使は適切だった」とし、フジ住宅側の控訴は棄却となりました。
まとめ

「表現の自由」をめぐる注目の裁判は、フジ住宅側の敗訴となりました。しかしながら「国民運動のシンボル」であるブルーリボンバッジの着用を国が禁止したことに疑問を抱かざるを得ないともいえます。
今回の裁判・訴訟をめぐり、フジ住宅に対してネガティブなイメージを抱いた方もいるかもしれません。
ヘイトハラスメントをめぐる訴訟においては「女性従業員へのヘイトハラスメントは認められない」「マスコミの報道は不適切」であると裁判所が認めています。
とはいえ、配布資料に差別的と受けとれる文言がそのままであったり、訂正せずに配布したことは、原告女性に対しての配慮が足りなかったのかもしれません。
現在は、差別的と受け取れる内容が配布物に含まれることがないよう十分に配慮しているといいます。
フジ住宅は、社員が心身ともに健康に働けるような職場作りに注力しており、正しい人事査定となるよう「360度査定」の導入や充実した福利厚生を設けています。
このような取り組みから、経済産業省による「健康経営優良法人2023大規模法人部門(ホワイト500)」に7年連続選定されており、ヘイトハラスメントを受けたとして提訴した女性従業員は現在も在籍しています。
本当にヘイトハラスメントをするような企業であれば、社員は定着せず、組織は成長しません。現在のような成功はしていないといえるのではないでしょうか。
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。





この記事へのコメントはありません。